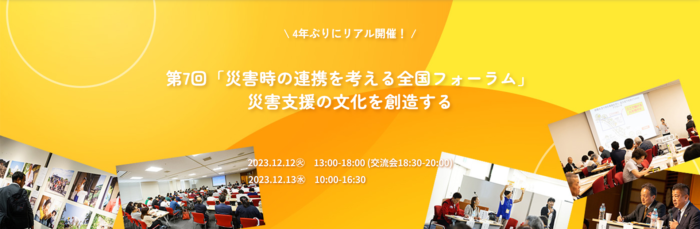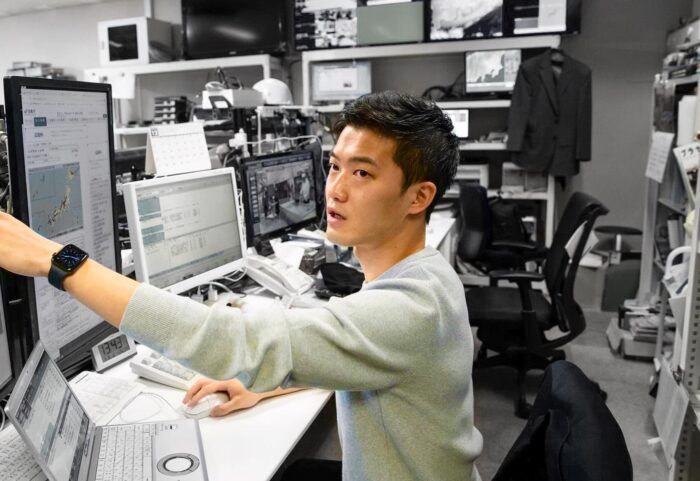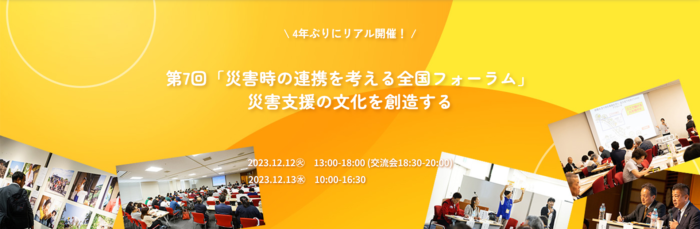
第7回災害時の連携を考える全国フォーラムへのご参加ありがとうございます。
当日(12/12(火)・13(水))の参加方法につきましては、下記をご参照ください。
1. 参加について
【日時】
12月12日(火)13:00~18:00(受付開始 12:00、交流会 18:30~20:00)
12月13日(水)10:30~16:30(受付開始 9:30)
【場所】
KFC Hall & Rooms(東京都墨田区横網 1-6-1 国際ファッションセンタービル)
最寄駅 都営地下鉄大江戸線 両国駅(A1出口)徒歩0分、JR総武線 両国駅(東口・西口)徒歩約7分
アクセス
【受付】
・会場へ到着されましたら、3Fのホール(ホワイエ)受付にお越しください。
・注文番号(請求書払いの方は、個人番号)とお名前をお伝えいただき、名刺フォルダーをお受け取りください。
・当日お荷物検査がございますこと、ご了承ください。
※注文番号は、Peatix 領収データに記載がございます。領収データにアクセスする方法
【分科会】
お時間になりましたら、申込の際お選びいただきました分科会へお越しください。
原則、事前申込者を優先とさせていただきます。
※注意事項※
事前申し込みの方の数の変動により、以下の分科会の部屋が変更となりました。
お間違いのないよう、ご移動お願いいたします。
12月12日(火)16:00-17:30
分科会1-2:Room107 → Room111
分科会1-5:Room111 → Room107
12月12日(水)10:30-12:00
分科会2-2:Room107 → Room111
分科会2-5:Room111 → Room107
【昼食】
・2日目(12月13日(水))の昼食につきましては、外の飲食店または、各自お弁当などをご持参ください。
・ラウンジや共用部での飲食は禁止されております。
・3FのHallもしくは、各分科会のお部屋で食べていただくことは可能です。
・ゴミが出た際ははゴミ箱へ必ず分別して廃棄いただくよう、よろしくお願いいたします。
【交流会】
・参加費を事前にお支払いいただいていない方は、受付にてお支払いください(4,000円)。
・当日ご参加をお申込みの方は受付にお越しください。
【その他】
・会場のwifiはご使用いただけません。
2. キャンセル等注意事項
· 当日のキャンセル・遅延・早退される場合の事前連絡は、必要はございません。
· 不測の事態による開催中止についてはJVOADウェブサイトでお知らせします。
· 地震、台風などの自然災害、その他やむを得ない事由により開催を中止する場合を除いて、参加費のご返金はいたしませんのでご了承ください。
· 会場では、主催者や取材メディアによる写真・動画撮影等が行われ、各種広報媒体で使用させていただきますので、ご配慮希望の方は、当日受付までお伝えください。
· セッションの様子・投影資料を全て動画撮影または音声録音して公開することはご遠慮ください。
· インフルエンザなどの感染症が流行っております。各自お気をつけください。
3. お問い合わせ
第7回災害時の連携を考える全国フォーラム事務局
TEL : 080-5961-9213
Email : info@jvoad-forum.jp
※当日メール等を確認できない場合がございますので、緊急の場合はお電話ください。